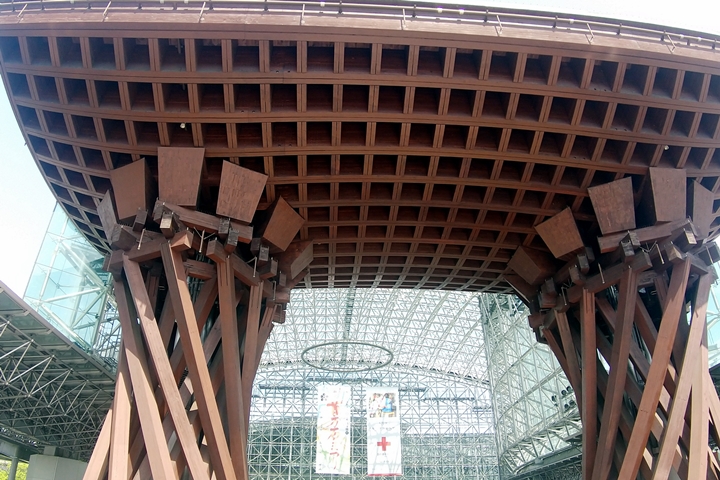斑鳩から生駒へと矢田丘陵をあるく
【奈良県・斑鳩町~生駒市 2023.5.11】
大阪府と奈良県の境に南北にそびえるのが生駒山地で、その最高峰である生駒山から東(奈良方面)をながめると、生駒山地と並行するように南北に隆起した丘陵が見わたせます。これが矢田丘陵で、南北の長さは13km、
標高は200~300m程度で、山が連なるというよりも隆起がうねるように続いています。
丘陵の南端は古い歴史をもつ斑鳩(いかるが)の地から始まり、山中には天武天皇の皇子・舎人親王(とねりしんのう)が開祖したという古刹・松尾寺があり、そこまではかつて斑鳩の法隆寺から参道がつづいていました。
さらに北には天武天皇の勅願で開かれた矢田寺があります。
そのような由緒をもつため、開発のすすんだ地域でありながら山中には車道がつくられることもなく、意外なほど深山を歩いているかのような雰囲気を味わえます。
今日は斑鳩の地を南北にぬけて丘陵に踏み入り、丘陵のおもに尾根にそって北端まであるき、生駒市のどこかの鉄道駅へゴールしたいと思います。
斑鳩



時間に余裕があるので先に法隆寺を拝観してゆこうかと思っていたのですが、GW明けの平日とはいえ、団体客を中心にすごい人出なので止めにしました。
この多数の人出ですが、GWをさけた団体客が重なったこと、いま東伽藍の夢殿で期間限定の特別公開が行われていること、それらが理由だと思います。




なんとビックリすることに、斑鳩の地にゴルフ場があります。この地でこれだけの開発をしたなら、おそらく古墳の二つや三つは××したのではないでしょうか。
このゴルフ場は半世紀以上も前に造成されたもので、きっと昔だから許可が下りたのでしょう。
矢田丘陵へ


松尾寺



天武天皇の第六皇子である舎人親王(とねりしんのう)は、天皇に即位こそしていませんが、飛鳥時代から奈良時代につながる激動の時代に、皇親派の政治家として重用されました。
舎人親王が、日本書紀の編纂に取り組んだのが42歳のとき。その大仕事の無事完成とみずからの厄除け祈願のために建立したのが、この松尾寺の起源と言われています。
そのため今は、厄除けお祓いの寺として有名です。

寺伝によると、9世紀に建立され、明治時代に再建されたものだそうですが、瓦など一部に古材が使われているとのことです。
【三重塔と五重塔の違いについて】
基本的には屋根の数が違うだけで、三重塔は3層の屋根をもつ一階建て、五重塔は5層の屋根をもつ一階建てです。
そもそもは釈迦の遺骨をおさめた巨大な供養塔であり墓標のようなもので、インドのストーパに相当します。
塔の上には登れません。窓は装飾用です。
背が高いのは上に登って周囲を見渡すためではなく、下から見上げて礼拝するためです。


丘陵をあるく




矢田寺



矢田寺は天武天皇の勅願により開基され、のちに地蔵菩薩を本尊として祀ったことから地蔵信仰の中心地として栄えます。
伽藍の建物は比較的あたらしく再建したものですが、仏像は重文に指定される奈良時代のものなどが多数収蔵されています。
またここは「あじさい寺」として知られ、梅雨の季節には境内がアジサイの花で埋まります。


ふたたび丘陵をあるく




【アクセス】JR斑鳩駅~斑鳩~松尾寺・松尾山~国見台~矢田寺・矢田山~小笹峠~近鉄南生駒駅 24000歩
【満足度】★★★★☆