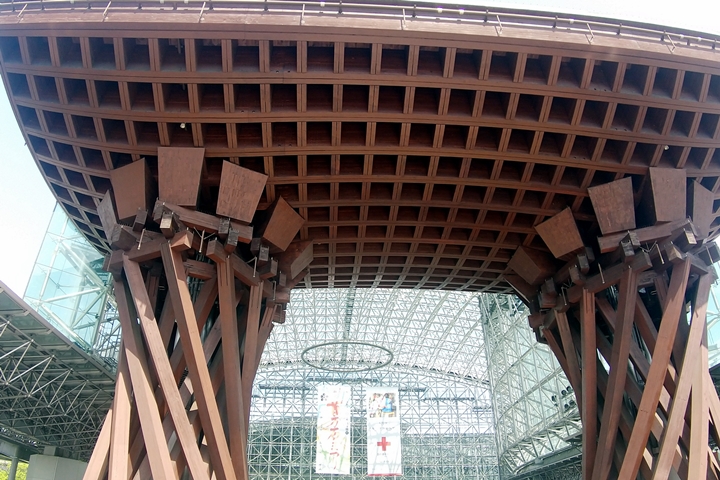能登半島一周 その壱(金沢~羽咋~能登海岸)
【石川県・羽咋市~志賀町 2023.5.17】
金沢市内でレンタカーを借りて、今日明日の2日間で能登半島を回ってみます。
まず今日ですが、羽咋市(はくいし)で気多大社と妙成寺を参詣して、能登半島の海岸線を行けるところまで北上してみます。
気多大社
気多大社(けたたいしゃ)は大国主命(オオクニヌシノミコト)を祀っています。
由来については神話の時代にさかのぼることになります。日本書紀ではスサノオノミコトの子息が大国主命とされていますが、この方は国づくりの神様です。
大国主命はまず最初に出雲の国を平定し(それゆえ出雲大社はこの方を祀っています)、そのあと船で能登へとわたりこの地に上陸したと伝えられています。
当時このあたり一帯は「越」とよばれ、地方豪族がそれぞれに支配するためヤマト王権の力がじゅうぶんに及ばない土地でした。そこで大国主命はいまで言う福井、石川、富山、新潟へと旅をつづけながら各地を平定してゆきます。その平定の旅の起点となった土地ということで、ここに祀られることになったわけです。
なお大国主命は、因幡の白兎を助けてあげた神話で有名な神様でもあります。

鳥居は両側に稚児柱とよばれる低い控え柱がつく、両部鳥居といわれるものです。
両部とは真言密教(仏を信仰する)において、智をあらわす金剛界と理をあらわす胎蔵界の「金胎両部」に神道(神を信仰する)を取り入れて解釈しようとするもので、ここに神仏習合の原点があります。
その神仏習合の思想をイメージとして形にすると、このような鳥居になるということで、神仏習合の歴史をもつ神社によく見られます。代表的なのは広島県・宮島の厳島神社の海中にたつ鳥居でしょう。





拝殿横からぬけると、神宮寺(神社に付随する寺)である正覚院があります。
妙成寺

妙成寺(みょうじょうじ)は日蓮上人の孫弟子にあたる日像上人が開いたとつたわる日蓮法華宗の寺院です。
前田家の祖・利家から寵愛をうけた側室ちよぼは男児を生みますが、その児がのちに前田家三代・利常となります。ちよぼは利家の死後みずから髪をおろして寿福院を名乗り、この妙成寺に帰依します。そのため妙成寺は寿福院を中興の祖と称えるほどに前田家とも強い関係をもちます。



ここ妙成寺は画聖・長谷川等伯ゆかりの地でもあります。
等伯は武家の次男として七尾に生まれますが、幼いころからその画才を認められ、請われて代々仏画師を系譜する長谷川家に養子入りします。
(もっとも当時の武家の次男ともなると、余程でなければ武士として生活してゆけるものではなく、体よく働き先をあてがわれたようなものだったのでしょう)

その長谷川家が日蓮法華宗に帰依していたことから、七尾時代にはおもに日蓮関係の寺の仏画を描くことが多く、ここにも「涅槃図」が残されています。
とはいっても安全保管のため絵は七尾美術館に預けられており、明日七尾へ行ったさいに特別展示会で見られる予定です。






能登海岸

「8番らーめん」は国内だと北陸地方以外にはほとんど店舗はありません。
ところが仕事をしていたころに年に数回ペースで出かけていたタイでは街々に店があり(まったく同じロゴ)、しょっちゅう利用していました。
懐かしいので、ちょうど昼食時でもあり、ここで「8番セット」(ラーメン+餃子)を食べることにしました。








ここからまだ北へと進むのですが、あまりにも長くなるので一旦ここで仕切ることにします。次回に続きます。
【アクセス】気多大社、妙成寺、能登海岸(巌門~世界一長いベンチ~ヤセの断崖~義経の舟隠し~トトロ岩)、金沢市内からレンタカーで回る
【入場料】妙成寺:拝観料500円
【満足度】★★★★☆