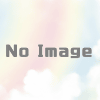長谷川等伯と久蔵の障壁画を見にゆく
【京都市内 2023.5.31】
室町時代末期から江戸時代初期、文化的には安土桃山と呼ばれた時代。画壇では当時絶対的な存在であった狩野家(派)に、ひとり立ち向かうかのように現れたのが長谷川信春(のちの等伯)でした。
信春は能登、七尾の豊かとは言いがたい武家の家に生まれます。ところがその才能を見込まれたというよりも、むしろ次男のため武家を継ぐわけにもいかず、体よく染物屋の家に養子としてもらわれてゆきます。
その家が純粋に染物だけを仕事としていたのなら、信春は一介の染物屋の親父で終わっていたはずです。ところがその家では代々日蓮宗の熱心な宗徒であったことも手伝い、家業として仏画を描いていました。
信春はめきめきと筆を上げ、能登ではその名を知られるほどの仏画師になります。そして父母が亡くなったのを機に、妻と長男の久蔵をつれて絵師として一旗揚げるべく、京の都にむかいます。
京では苦節の末、茶人の千利休、豊臣家の五奉行のひとり前田玄以らの知己をえて、寺院や大名屋敷の障壁画、襖絵を手掛けてゆくようになります。
そのなかで長谷川等伯の人生における一番の大仕事は、秀吉が愛息・鶴丸の死を悼んで建立した祥雲禅寺の書院を埋めつくした襖絵の数々ではないでしょうか。
ことし3月に観梅がてらに訪れた際には、宝物殿を新築中で見ることができなかったのですが、今日あらためて出向くことにしました。
智積院すなわち祥雲禅寺

さきにも書きましたが、秀吉が幼くして亡くなった鶴丸の菩提寺として建立したのが、祥雲禅寺です。
しかし豊臣家が滅亡し徳川の時代になると、家康はかつて秀吉から攻撃され迫害された紀州・根来寺の仏僧をまねき、祥雲禅寺の境内をそのまま真言宗の寺院として改宗したうえで改築することを許します。



大師堂は、言わずとしれた真言宗の開祖である弘法大師・空海上人を祀っていますが、その伽藍のさらに奥にある蜜厳堂には、高野山から分派した真義真言宗を開祖し、根来寺をひらいた覚鑁(かくばん)上人を祀っています。
(覚鑁上人が高野山を下りて真義真言宗をひらくに至る経緯は、奈良の長谷寺を訪ねたさいに書いたのでここでは省きます)
智積院で、大師堂や密厳堂まで足をむける人はほとんどいませんが、むしろこの奥まった一角こそ味わい深い穴場です。


長谷川等伯・久蔵親子 vs 狩野派・狩野永徳

この宝物館の展示品は長谷川等伯、久蔵らにより禅祥雲寺の書院にえがかれた襖絵と障壁画がそのほとんどすべてですが、常設のため開館日であればいつでも見られます。
おおきな一室がその展示場にあてられていて、四面ぐるりが金箔をつかった襖絵と障壁画で埋められており、圧倒的でありながら心の襞に染み入ってくるような感動を覚えます。
(あくまで個人的な感想です)
宝物館内はもちろん撮影禁止のため、等伯の「楓図」、久蔵の「桜図」などの画像が手元にありません。
ネット上で拝借できる画像を使って、とも考えましたが、これらは後日もっと整理して「読みあるく銘銘伝」にまとめるつもりですので、今回は仰々しいタイトルをぶち上げたものの、「未遂」で終わりとします。
本法寺へ烏丸通りを北へあるく

長谷川信春が七尾時代に日蓮宗徒であり仏画を描いていたことは冒頭で書きましたが、京都ではまず日蓮宗の本山である本法寺をたずね、しばらくそこに滞在しています。
その本法寺まで行きます。智積院からだと1時間ばかり北東へ歩くことになります。



烏丸通りを御所まで北へと歩くと、100mほどの間隔でならぶ信号という信号のすべてが目前で赤に変わるという厄介な経験をしました。
そのためここに来るまでに見込みよりも1.5倍ほどの時間が掛かってしまいました。べつに急いでいるわけではないにしても、やはり厄介です。




本法寺



500円を払うと、信春の晩年、等伯を名乗るようになってからの作である涅槃図(レプリカ)が庫裏で、「巴の庭」とよばれる名園が書院で見られます。
見た感想ですが、涅槃図はレプリカとわかってはいたものの、そうとうに稚拙なもので、智積院ですばらしい障壁画を見てきただけにショックでした。
毎年3月中旬から4月中旬まで真作を特別公開しているようです。この時だけは1000円に値上がりしますが、見るのであれば、「真作1000円コース」をお勧めします。


近くの妙蓮寺へ足をのばす

観光客が拝観料を払ってでも訪れるような有名寺院を別にして、一般のお寺の収入源は檀家からのお布施と護寺費(年会費のようなもの)によります。檀家一軒あたりのお布施と護寺費は平均して年4万円ほど(?)とのこと。
いまでは檀家も激減しており、(500軒あれば2000万円ですが、200軒しかなければ年間収入が800万円ということ)、相当に厳しいのか境内を駐車場として貸しているところをよく見かけます。
妙蓮寺は月極(?)で駐車する車でいっぱいで、寺院としての趣がないので早々に引き上げました。絵も見れたようですが、等伯の作品でもないし、まあいいかということで。
【アクセス】京阪七条駅~智積院(祥雲禅寺)~(烏丸通をあるく)~本法寺~妙蓮寺~京都地下鉄今出川駅
【入場料】智積院・宝物館:500円 (庭園はべつに300円)、本法寺・庫裏の涅槃図と書院の庭園:500円
【満足度】★★★☆☆(この評価には、智積院宝物館の障壁画鑑賞は含めていません)