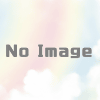大和の国有数の巨城・龍王山城址を訪ねる
【奈良県・天理市 2023.8.19】
今日は奈良県北中部にある龍王山を登りに行きます。
この龍王山は 今年3月に登って間もないのですが、今回の目的は、いま戦国の武将・松永久秀に関して調べているところから龍王山城址をあらためて見ておきたいと思い立ち、その城址が龍王山のまさに山頂から稜線にそって残っているゆえ、必然的に登ることになった次第です。
龍王山城はこの地の豪族・十市氏により築かれたのが始まりです。十市氏の時代にどの程度の規模で、どれくらいの建造物があったのかは定かではありません。
その後一時的に宇陀松山城から進出してきた秋山直国のものとなりますが、やがて織田信長の上洛の際に臣下となった松永久秀がその織田軍の援護を受けて、大和国の覇者をめざす筒井順慶を駆逐、その勢いで龍王山城も我が物とします。
崇神天皇陵横から入山する

前回は長岳寺横から登ったので、今回は少し南にある崇神天皇陵横の道から入山します。










龍王山城はいわゆる龍王山の山頂にある南城と、標高としては少し低い別山にある北城に分かれていますが、いまはこの舗装道によって行き来できるようになっています。
南城






南城は単純に縦、横に曲輪がつらなる、連郭式の城跡でした。遺構としては、曲輪、堀切などが残るだけで、おそらくは元々石垣もなかったのではないかと考えられています。
松永久秀は多聞山城、信貴山城という名城を築いた、城づくりに関しては名人といえる偉才の持ち主であり、石垣以前にこの曲輪配置の稚拙さは、どう考えても久秀の頭から生まれたものとは考えられません。
あくまで推測ですが、南城は十市氏の時代につくられたもので、久秀はさほどには手も加えず物見の目的で使用していたのであろうと思います。
北城







北城は本丸を中心に各曲輪が輪のようにかこむ、輪郭式になっています。
堀切、土塁の配置も巧みで、石垣も積み上げられていたようで、防御機能において南城とは雲泥の差です。
この北城は間違いなく松永久秀の手によるものと思われます。どのような建築物がどのように配置されていたのか、ぜひ見てみたかったものです。
なお龍王山城は、松永久秀が信長に討伐されて後、顧みられることもなくそのまま廃城となる運命をたどります。
長岳寺横へ下山





ここからもう一つの目的地である大和神社まで、平地の一般道をあるくことになりますが、距離にして1.6km。
通常ならば大した歩程ではないのですが、現在気温は36度に達しています。しかも山をひとつ登ってきたところで大量に汗をかき、体力も消耗しています。
ここで無理をして炎天下を歩いたのがあとになって身体に応えることになりました。
帰りの電車では頭痛に悩まされ、翌日一日は倦怠感でぐったり。
大和神社

大和神社(おおやまとじんじゃ)は日本大國魂大神をまつる日本最古の神社のひとつですが、同時に戦艦大和の守護神として、艦内に祀られていました。




【アクセス】JR柳本駅~崇神天皇陵~龍王山(龍王山城・南城~北城)~長岳寺~大和神社~JR長柄駅 20,000歩
【満足度】★★★☆☆