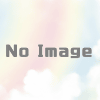徳川幕府が西国の抑えとして築かせた明石城
【兵庫県・明石市 2023.9.9】
徳川家は幕府をひらいてのちも、かつて豊臣家に臣従した、いわゆる西国大名、なかでも毛利家をとくに警戒していました。毛利の軍勢が東進してくることを想定して、姫路城に家康のかつての重臣・本多忠勝の嫡男・忠政を配します。ちなみに忠政の正室は家康の孫娘です。
二代将軍・秀忠はそれでも安心できなかったのか、信濃松本藩より小笠原忠真を播磨の地に転封し、姫路城の後詰めとしておよそ10里(40km)東の明石の地に、あらたな城を築くよう命じます。小笠原忠真は本多忠政の協力をえて、2年のうちに大方の造作を終えます。これが明石城です。
なお小笠原忠真は家康の曾孫にあたり、さらにその正室は本多忠政の次女であり、家康の養女となってのち忠真に嫁いでいます。密接な姻戚関係でむすばれた大名のみを信用していた徳川家の細心さがうかがえます。
三重櫓


これが明石城を代表する景観です。
坤(ひつじさる)は方位で南西のこと、巽(たつみ)は南東のこと。要は「南西の櫓」と「南東の櫓」というだけのことです。
ところで明石城は、なによりも急いで築く、さらに低予算で築くことが前提であったため(と勝手に推測しているのですが)廃城にしたかつての城のパーツを移築したり、廃材をつかったりと再利用を徹底しています。坤櫓は豊臣秀吉の最後の居城であった伏見城から、巽櫓はもともと近くにあった船上城から移したものと伝わっています。






本丸

案内板でみるとよく分かりますが、坤櫓と巽櫓は本丸南面の西と東に位置しています。
そして石垣と堀以外ではこの両櫓だけが遺構として残っている建造物です。

坤櫓には無料で入ることができます。展示品にはめぼしいものはありませんが、櫓からしか見られない風景を楽しめました。




この明石城では、天守台をつくったにもかかわらず建物としての天守が建てられることはありませんでした。理由は「幕府に気を使って」ということになっています。では幕府の何に気を使ったのでしょうか。
推測してみましょう。
徳川秀忠ですが、有名な「武家諸法度」を交付しています。そのなかで「諸国の諸侍は倹約を心がけるように」と明記されています。
そもそも明石城の築城を命じたのは徳川秀忠であり、さすがに命じた以上は普請費用が渡されました。
さて小笠原忠真ですが、必要最低限の造作を終えた時点でわたされた金はすべて使い切り、本丸御殿などは自費でつくったものと思います。あくまで推測ですが、ドケチの徳川幕府が大名個人の住居である御殿の建築費用まで出してくれるとは思えません。
それでは天守(または天守閣)はというと、これは戦う上で必要なものではなく、藩主すなわち城主の力を誇示する、いってみれば「見栄え」として建てていたものです。そうであれば、「倹約を心がけて」天守の建築は中止したと考えるのが妥当ではないでしょうか。
石垣、堀







城郭の北面(観光客からすると裏側)は自治体に整備する金がないのか、「公園」というより「休閑地」になっていました。
石垣に植物が繁茂しているのは、その植物が石垣の隙間に根を蔓延らせているということです。
すると降雨時に石垣の隙間に流れ込んだ雨水はすんなり流れ出ることができず、石垣の隙間にたまります。この水の重みで石垣の石同士がしだいに滑って隙間を大きくし、さらに多量の水がたまるようになり、やがて自然崩壊します。
まあ地震がないかぎり今後30年や40年は大丈夫でしょうが。



【アクセス】JR明石駅から徒歩すぐ
【入場料】無料
【満足度】★★★★☆