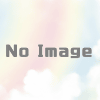秀吉が朝鮮出兵のためだけに造らせた名護屋城
【佐賀県・唐津市 2025.7.11】
秀吉は木下藤吉郎を名乗っていたころは、明るいキャラクターで好漢といって良いと思います。
そこから出世して、羽柴秀吉を名乗るころからずいぶん狡猾な顔が見えはじめますが、それでも成り上がる姿とあわせて見れば英傑と評価できます。
ところが天下統一をなしとげ、豊臣秀吉を名乗りはじめたときから理解しがたい行動が目立ちはじめます。欲と見栄に毒されたのだろうでは説明のできない、正常な判断力がうしなわれついに狂気にとりつかれたのか。
狂気とするなら、その最たるものが朝鮮出兵かもしれません。
秀吉の外征(俗にいう唐入り:当時の中国は明の時代ですが、通称として唐とよんでいた)といえば朝鮮出兵ということになりますが、もともとは朝鮮を切りしたがえて続いて明に侵攻するというのではなく、秀吉の意識のなかではどうやら端から朝鮮が日本に対して反抗するはずがないと決めつけていたようです。
そこで、明(中国大陸)を征圧するための軍をすすめる上で朝鮮半島を通るゆえ「征明嚮導(明を征圧に向かうときにはその道案内をしろ)」と秀吉は一方的に命じます。
朝鮮王国は公的にも明に対して臣従しています、明国の保護下にあるとも言えます。一方日本に対してはなんら主従関係はありません。
秀吉の使者はことを荒立てないよう「仮途入明(明に入るときには道を貸してくれ)」と表現をかえて要請しますが、朝鮮王国の抱く不快感は警戒感へとかわってゆきます。
名護屋城

大手口前に入城口があります。
入城料は無料ですが、遺跡保存のための協力金として一人100円を任意で払うとここにアップしたガイドマップをもらえます。
協力金は別にして、この地図のためだけでも100円は払うべきです。
大手口から東出丸へ



右側の平地が長屋建物跡地、その先の隆起部が東出丸

では明と日本との関係はというと – – –
歴史をさかのぼって、室町時代の三代将軍・足利義満は勘合貿易による莫大な利益を得るため明にたいして臣下の礼をとり、形式的には日本から明国への朝貢というかたちで貿易をはじめます。
義満にとっては明と日本との上下関係などにはさらさら興味もなく、実利を取ったということでしょう。あるいはこのときには日本の国力はあまりに弱く、明国の下につくことにプライドがどうこうなどと勘案することもなかったのでしょうか。
ともかく義満がむすんだ明との上下関係は、室町時代の末期からつづく秀吉の時代にはまだ確固として残っていました。秀吉がそれを知らなかったか無視したかというだけのことです。
(この明との上下関係は外交のうえでの形式上のことですから、日本国のなかでこれを屈辱と感じる風潮はなかったはずです。)
三ノ丸




秀吉が明の征圧、さらには東アジア全体の統治を考えはじめたのは島津征伐をなしとげたころからと考えられます。このときに九州を平定したことで、明への進攻の道が拓けたと感じたのでしょう。
すなわち秀吉のとっては、明を征圧することは島津を征伐するのとおなじ次元のことであり、東アジアを統治するのは九州を平定することの延長線上にあることと認識していたのではないでしょうか。
本丸




天正15年(1587年)島津征伐→九州平定
天正18年(1590年)小田原征伐→関東・奥羽平定
そして天正20年に最初の朝鮮へむけての出兵がおこなわれますが(文禄の役)、その前年の天正19年には見逃せない事件が3つ立て続けに起きています。
1月、唐入りにつよく反対していた秀吉の弟・秀長が病没。
2月、茶頭の千利休が切腹を言いわたされる。その切腹を言いわたされた直接の理由ではないものの、文化人の利休が明や朝鮮に討ち入ることに反対意見をもっていたことは事実。
そして8月、秀吉五十をすぎてやっとめぐまれた跡取りである長男の鶴丸が病死。
秀長と千利休の死で忌憚なく唐入りに反対する人物がいなくなったところに、溺愛する息子の死。ここでタガが外れたのか、アタマのネジが飛んだのか、あるいはなにかに取り憑かれたのか、このときからかつての茶目っ気もユーモアも持った秀吉は完全に失われ、まったくの別人になったと考えるべきでしょう。
本丸、天守台






秀吉が唐入りを決断した理由については、
➀日本国内で切り従えた武将たちの忠誠心を再確認するため、あるいはより苛烈な掃討戦に従軍させることで結束をかためるため。
➁ほかの武将たちに従軍や城普請により結果的に多額の出費を強いて(反抗する)力を削ぐため。
③戦功のあったものにあたえる恩賞としての土地が日本国内では不足するため、あらたな土地をもとめて。
どれも的外れではないというだけで、これが理由と断言するには弱すぎます。
ほかにも、
④国内の平定がおわり戦がなくなったがために、いわゆる戦争景気が失われた。そこで「景気対策」としておもに石田三成が中心になって策謀した。
というものもありますが、これなどは三成嫌いの人が捏造したものだと思います。
馬場から曲輪へ



五奉行のひとり浅野長政(官位が弾正少弼)の居館があった

それではなぜ誰もがすくなからず反対した唐入りが実行されたのでしょうか。
『文禄・慶長の役 空虚なる御陣』のなかで著者の上垣外憲一氏が興味深い見解を述べておられます。
水面下で秀吉が五大老の首席の徳川家康と次席の前田利家にたいして、両名の負担には配慮するので唐入りに賛成して後押ししてくれと頼んだのではないか。
五大老のトップ2人が賛同すれば、さずがに異を唱えるものはいないでしょう。
その後を調べてみると、徳川家も前田家もこの唐入りに関しては大藩であるにもかかわらず兵の派遣はただのひとりもなく、実質的に後方支援のみです。




秀吉がなぜ唐入りに執心し、あらゆる反対意見にも耳を貸さず強攻したのか。
その謎にはいまだ明確な回答は出せぬままですが、時間をかけて調べてみるつもりです。
こうして名護屋城をおとずれてその壮観に圧倒され、いましばらくは秀吉唐入りの題目から離れられそうにありません。
山里口


【アクセス】車にて
【入城料】資料館もともに無料 / 保護のための協力金は任意で
【満足度】★★★★★ (協力金は100円となっていましたが、満足度がたかく1000円払いました)