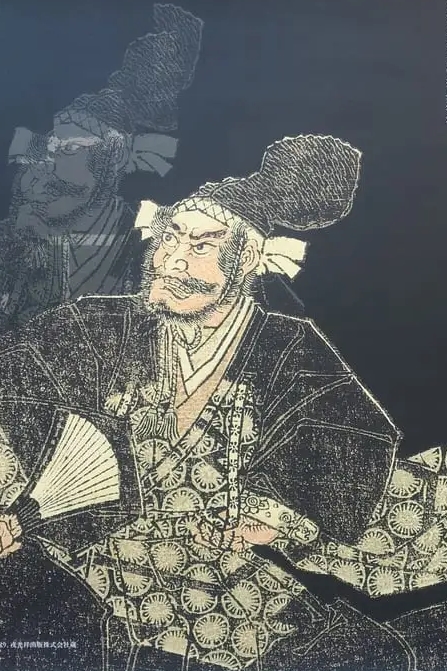濃姫(帰蝶)の謎・濃姫はどこへ消えたのか – 雨読寸評 1
山岡荘八氏の小説『織田信長』では、濃姫は本能寺の変の際にも信長と行動をともにしており、その事変では自ら薙刀をふるって奮戦したことになっています。
この薙刀をふるってというのは、のちの世の講談などで語られたもので、完全な創作ですからあり得ない話です。
山岡氏の『織田信長』は時代考証はずいぶん大雑把で、そんなわけないだろうと突っ込みたくなる部分もあるのですが、とにかく読んでいておもしろい。なぜ面白いかといえば、山岡氏が当時を代表する国民作家であったためか、読者を楽しませることを主眼にしているようです。よほど信長のことが好きなのか、信長のよい面が前面というより全面に出てきて、さらに濃姫にいたっては読みながら恋心を覚えるほどに魅力的です。
先にも書いたように時代考証については十分とは言い難いですが、小説が書かれる本来の目的である「読んで楽しい、おもしろい」という意味では良品だと思います。
山岡荘八『織田信長』 ★★★★☆
鈴木輝一郎氏の小説『信長と信忠』は、信長と信忠がW主役かと思って読んでみたところそうではありませんでした。父信長の目を通しての跡取り息子信忠を描くというというのが表向きで、その実は信長が信忠の成長を見ながら単純に喜ぶのではなく葛藤する姿を描き、父信長さらには人間信長を斬新な切り口で読者の前にさらして見せる、といったところでしょうか。
残念ながら信忠の描き方があいまいで、とくに父信長の強烈な個性をどのように受け止めているのかがはっきりしないので、信忠もぼんやりしていれば、その信忠を見つめる信長に対しても何に葛藤しているのか感情移入ができません。その意味ではわざわざ評価する作品でもないのですが、ここに登場する、しかも信長と信忠両者にからむ濃姫の存在感は圧巻です。
信長が秀吉のいる備中高松へむかうに先立ちひとまず上洛しますが(このとき宿泊先の本能寺で討たれる)、安土城を発つ前に信長と濃姫がかわす会話は絶妙です。
一部抜粋します。
– – – 信長は美濃の方(濃姫)を抱きしめている自分に気づいた。唇をかさねる。
「帰ったら」
「お帰りなさったら?」
「やろう」
「生きてお帰りになれれば」
「誰から誰への褒美なのやら」
「ほんに」
鈴木輝一郎『信長と信忠』 ★★★☆☆

岐阜城は金華山の山上に城郭があり、麓に居住部分があったそうです。
そして岐阜城にある説明や解説では、この居館に濃姫の部屋があった、あるいはここで濃姫が暮らしたと明記(明言)しています。
画像は【aruku-17】より
https://yamasan-aruku.com/aruku-17/
諸田玲子氏の小説『帰蝶』では、濃姫(作品の中ではずっと帰蝶です)は早死も離縁もせず、それどころか本能寺の変以後も長く生き続けます。しかし信長と結婚してのち重い病にかかり顔にあばたができてしまい、そのことを恥じて以後は人前に出ないようになったため歴史の表から消えてしまったと設定しています。
これはおもしろいというか、女性ならではの発想だと思わず膝をたたきました。
しかし膝をたたいたのはその時だけで、全体を通して感動も感心もほぼありませんでした。
諸田氏は「あとがき」で、残虐無比な殺戮を平然としてのける信長のことを身の毛がよだつほど嫌いだと書いておられますが、当時の比叡山がいかにトンデモナイ状態だったのかを御存じなのでしょうか。(信長が比叡山を殲滅したのは正しいと考える人は多々いるでしょう)
あるいは本願寺の顕如や教如が「進まば往生極楽、退かば無間地獄」と、「戦いで死んでも極楽へ行ける、退き逃げればその場で死ななくても後に地獄に落ちる」と、死兵どころかただの死ぬだけのために数千数万の信者を煽りにあおった事実をどれだけしらべたのでしょうか。(だったら教祖自身はなぜみずから先方に出てきて進まないのかの矛盾を考えれば、腹が立ってきませんか?)
ほかにも史実と矛盾している点はありますが、それらは小説ゆえにアレンジしたといえばそうかもしれません。しかし私が読んだ文庫版の383ページには、蒲生忠三郎(のちの氏郷)が本能寺の変の直後、安土に居る帰蝶をふくめた信長の家族を救出にきて、これから避難する日野の城(蒲生氏の居城)はここより2里、と忠三郎に言わせるだけでなく、2里のあとには(約8キロメートル)と注釈まで加えているのですが、実際には安土城から日野城まで24km、小説のなかにある「腰越と呼ばれる安土城の南端の辻」をいまの「南腰越」と想定しても23kmあります。いかに小説とはいえ、安土城から日野城の距離までアレンジする必要はないでしょうから、きちんと調べていないということでしょう。
諸田玲子『帰蝶』★★★☆☆
篠綾子氏の小説『岐山の蝶』も、濃姫(作品の中では、帰蝶あるいは姫)が主人公の作品です。
濃姫は、父・道三に仕える明智光秀と互いに思いを寄ながらも、武家の娘の運命にしたがい織田信長の元へと嫁ぎます。その信長に対しては嫌悪することはないものの、お互いに心を開くことができず、そのため光秀への想いもあって葛藤しながら日々を送ることになります。
まず信長の描き方があまりにも平面的で、さらに光秀にいたってはそこに立っている案山子を描写しているかの如くで、そのため濃姫の感情の起伏にいまひとつ同調できません。
この作品の中では、幼年時代に寺へ預けられやがて出奔してしまう実姉がいる設定で、濃姫がいったんは信長のもとをはなれ京へ上るのですが、そこでこの実姉と出会い – – – というあたりからだんだんと著者オリジナルの世界に入ってゆき、小説だから作者の想像力で自由に描くのは良いのですが、なんとも都合よく出会ったり別れたり、しかもこの濃姫はまちがいなく濃姫なのだと裏書きするかのように、当時の歴史的な事件を速攻で書き並べて時代背景をあわせて見せたり。
そして最後はなんとなく信長の正室・濃姫の物語だったんだなとぼんやり納得して本を閉じました。
篠綾子『岐山の蝶』★★★☆☆


滋賀県蒲生郡日野町には、蒲生家の居城であった日野城の跡が残っています。
現存する『氏郷記』にも「信長公御台(みだい)」を安土城から日野城へ避難させた記録はあるそうですが、そこに記された「信長公御台」が濃姫のことなのかとなると確かではありません。
画像は【aruku-44】より https://yamasan-aruku.com/aruku-44/

京都・大徳寺総見院にある織田信長一族の墓のならびに、濃姫の墓(手前)もあります。
画像は【aruku-35】より
https://yamasan-aruku.com/aruku-35/
楠戸義昭氏の研究書『女たちの本能寺』は、濃姫や明智光秀の正室・煕子など信長と光秀を取り巻く7人の女性が、本能寺の変によりいかに運命を変えたのかを語っています。
7章(7人)のなかでは「第一章・濃姫」と「第四章・お鍋の方」がここに関係しています。
大徳寺総見院にある墓には「慶長十七年壬子七月九日信長公御台」とあるそうです。ここでも御台(みだい)とあるので、一般には信長の正室と解釈されたようなのですが、正室・濃姫が早くに亡くなっていれば、信長がもっとも愛情をかたむけたお鍋の方を婚姻こそ結ばないものの正室(御台)に相応するものとして待遇していても何ら不自然ではありません。
さらに濃姫の死亡したのがいつであるのかははっきりしないものの、お鍋の方については慶長17年6月25日であることが記録されており、多少のズレはあるものの、この御台とはお鍋の方のことではないかと書いています。
また当時の正室の定義について書いてある項目では、正室は死んだ夫の菩提を弔うことが重要なつとめであったことを述べ、岐阜市にある信長の菩提寺・崇福寺の墓をお鍋の方が守りつづけた事実から考えても、信長の後半生に寄り添った「正室」はお鍋の方であったことが有力なようです。
すなわち濃姫は早世していた、と考えるべきかもしれません。
楠戸義昭『女たちの本能寺』★★★★☆

画像は【aruku-18】より
https://yamasan-aruku.com/aruku-18/