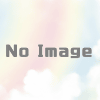混雑する京都市内を避けて、長岡京の光明寺で大当たり
【京都府・向日市~長岡京市 2023.7.15】
久しぶりに京都の寺社を見に行こうと思ったものの、よくよく考えてみるとこの日は3連休のはじまりで、しかも今日から祇園祭がいよいよ佳境にはいるため、まさに言語を絶する人出が予想されます。
さらに天気予報によると京都市内の予想最高気温は36度。
猛暑のもとで人でごった返すなか寺社見物をたのしむ場面はどうしてもイメージできません。
そこで大阪を基点にいうと、京都市の手前にあたる向日市、長岡京市あたりでめぼしい寺社はないかと調べてみたところ、いくつか見つかりました。なかでも長岡京市にある光明寺は紅葉で有名なところですが、紅葉が美しいということは青もみじも美しいはずです。
ありがたいことに(というと同じ時に京都市内を散策する人には申し訳ないのですが)、京都盆地から南に外れているためかこの一帯の予想最高気温は33度。正午過ぎまでに引き上げるようにすれば、もっとも暑い時間帯でも30度そこらとなり、これなら最後まで楽しめるレベルでいられます。
向日神社



向日神社はそもそもは向神社であったようで、社伝によると718年の創建とのことですからずいぶん歴史の古い社です。
護火および祈雨の神である火雷大神、五穀豊穣の向日神、さらに神武天皇とその御妃の御母である玉依姫命(玉櫛姫)と、神話の時代の神様を祀っています。

渡廊下をくぐって本社の後方に抜けると、木立越しに街並みを見下すことになり、この神社が小丘の上にあることがわかります。
高さでいうと100mぐらいある急階段をくだると、住宅地に出ますが、そこから長岡京市に変わります。
乙訓寺

徒歩20分ほどで乙訓寺(おとくにでら)に着きます。
乙訓寺は推古天皇の勅願により、聖徳太子が開祖となって建立したと伝えられていますが、とにかく関西には「聖徳太子開祖」の寺はあまりに多いので、伝承の域をでません。
しかし史実として確実なことは、早良親王はここに幽閉され配流の途上でなくなり、怨霊として祟り神になった事実です。

早良親王(さわらしんのう)は桓武天皇の弟であり、次の天皇候補すなわち皇太子でした。
桓武天皇は平城京における仏教勢力の過大な影響を憂慮して、(平安京のまえに)長岡京へ遷都を計画します。その実務をおこなう責任者が早良親王と藤原氏の実力者・藤原種継ですが、その種継が暗殺されたことから早良親王は首謀者として拘束されることになります。
その拘束されていたのが、この乙訓寺です。早良親王は絶食して自分の無実を訴えますが、聞き入れられることなく、淡路島へ配流となり、その途上でまさに憤死します。

ところが早良親王の死からのち、桓武天皇の身辺で次々に凶事がおこり、これら不幸不吉な出来事が続発するのは早良親王の祟りだと噂されるようになります。
そもそも祟りとか怨霊を恐れるのは、無実の相手を陥れた側のうしろめたい気持ちから出てくるもので、その意味では早良親王は無実で、桓武天皇の側になんらかの意図的なものがあったのでしょうか。
早良親王は崇道天皇という追尊の位をあたえられ、さらに怨霊を鎮めるため京都や奈良にある崇道神社に祀られています。(すなわち崇道神社はすべて怨霊神社です)
光明寺
乙訓寺から徒歩15分ほどで光明寺に着きます。
光明寺は、平家物語にも出てくる源氏の武将・熊谷直実(くまがいなおざね)が出家してのちに創建した寺です。
平家没落の起点となった一ノ谷の戦い(いまの神戸市西側)に勝利した源氏方は、周辺の掃討をすべく個々に見回りをおこなっていました。そのとき熊谷直実は須磨の海岸で逃げ遅れた平家の将を見つけます。
勝利の勢いそのままに直実が相手を組み伏せると、それは見た目もうつくしい若者で、いかにも高位のものと思われます(実は平清盛の甥にあたる平敦盛でした)。その首を取れば大殊勲です。しかし相手は自分の息子と同年くらいの若者、しかもその目は涼しげで怒りも恨みもありません。しかも直実の躊躇を見て取ったのか、若者(敦盛)はためらわず自分の首をとって手柄にするよう勧めます。
直実はあらゆる感情を殺してそのときは敦盛の首を取るのですが、この事件は直実の心に大きな影を落とすことになり、やがて直実は出家して高野山に上がります。
のちに直実は法然上人に出合い、その弟子となり、この光明寺を開山することになります。



総門から御影堂への道は、絵画のように美しいもので、この道を歩くだけでもわざわざ来る甲斐があります。
階段の傾斜が緩やかなゆえか、風景に厳かさはないのですが、優しさがあります。それゆえ総門をくぐり御影堂にたどり着くまでに、ゆっくり穏やかに仏の慈愛に包み込まれてゆくような感覚をおぼえます。



阿弥陀堂の奥に法然上人御廟や納骨堂がありますが、一般参拝者はこれより先には立ち入れません。
それでも御影堂は中まで入らせてもらえたので良しとしましょう。




長岡天満宮

光明寺から徒歩20分で長岡天満宮です。
光明寺を出たのが11時半ごろでしたが、この20分の歩行はずいぶん暑く、日傘を持っていたのが救いでした。男性で日傘を使っている人はあまり見かけませんが、きわめて有効な暑さ対策になりますので是非おすすめします。

全国にある天満宮は、もとはと言えば菅原道真の怨霊を鎮めるために造られたもので、先ほどの早良親王と同じように恨みの逸話がのこっていますが、以前北野天満宮に参詣したさいにそのことは書きましたのでここでは省きます。
いまでは祟りを恐れるなんていう物騒な話は忘れられ、学問の神様として慕われているのでそれでよいのではないでしょうか。




【アクセス】阪急西向日駅~向日神社~乙訓寺~光明寺~長岡天満宮~阪急長岡天神駅 14000歩
【料金】すべて無料 (光明寺は紅葉の時期のみ拝観料1000円必要なそうです)
【満足度】★★★★☆